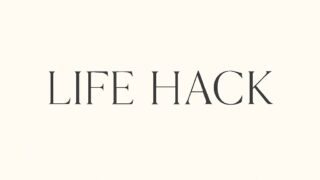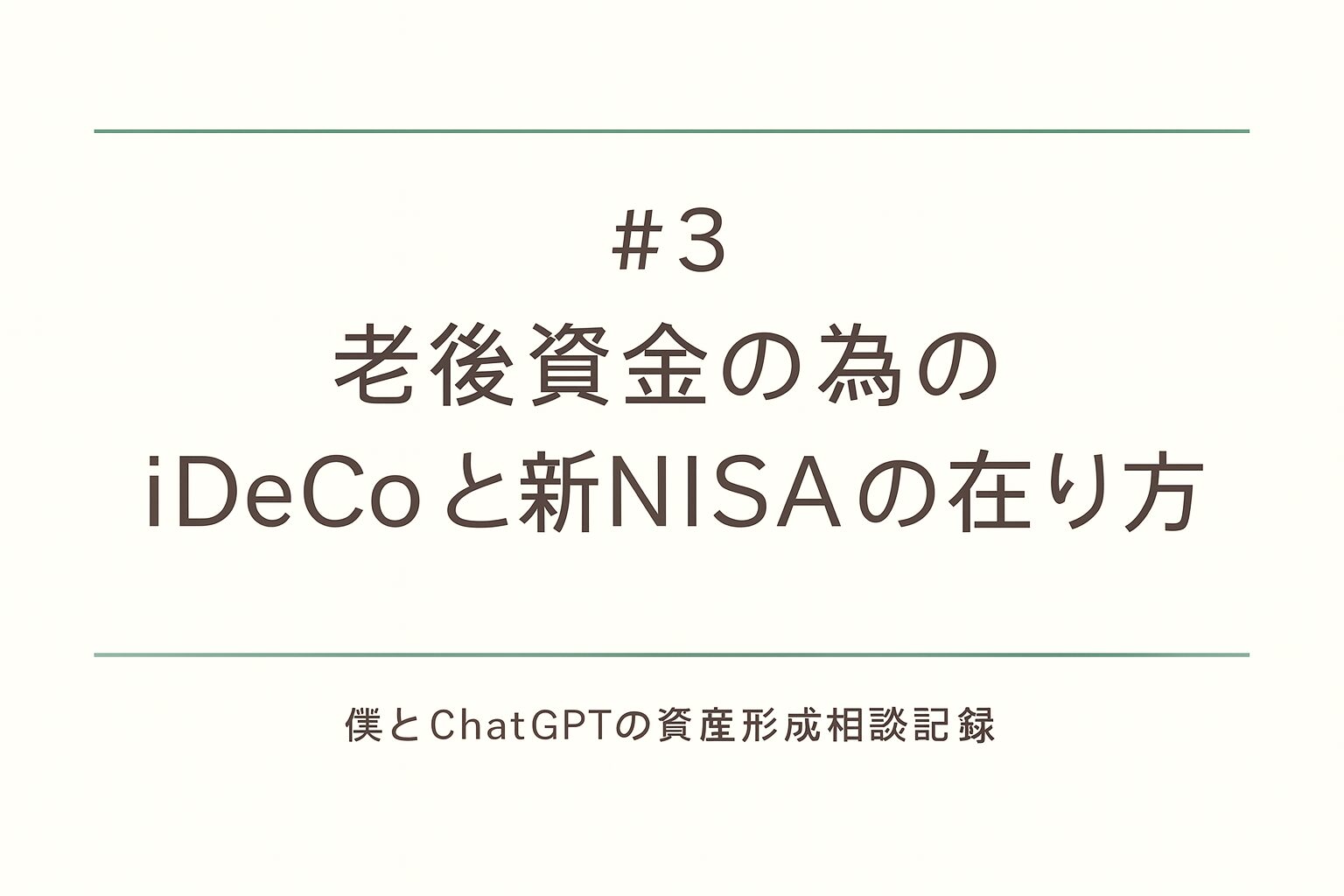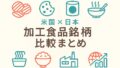あなた:
よく新NISAで老後資金を作っていくという人がいるんだけど、節税面からしてもiDeCoの方がいいよね?2027年からアップデートされる予定ではあるからそれだと利用するの必須レベルではあると思うんだけど。
ChatGPT:
思考時間: 2m 10s
結論:老後資金を作る目的なら “iDeCo優先 → 残りを新NISA” が基本戦略でOK。
なぜiDeCo優先?
- 掛金がそのまま所得控除(住民税10%+所得税の限界税率ぶんが即・節税効果)。運用益も非課税、受け取り時も控除枠あり(退職所得控除/公的年金等控除の対象)。三井住友銀行+1
- 2027年前後に大幅拡充:会社員等の上限が月6.2万円、自営業は月7.5万円へ。iDeCoの加入年齢も70歳未満までに拡大予定(施行は公布後3年以内の政令で定める日)。拠出余地が一気に広がる。厚生労働省+1
一方、新NISAは?
- 年間360万円・生涯1,800万円まで非課税、無期限運用。売却で総枠(1,800万円)は再利用できる(※同一年の年間枠は復活しない)。拠出時の所得控除はない=“節税の即効性”はiDeCoに軍配。七十七銀行+1
節税インパクトの目安(ざっくり)
- 年間節税 ≒ 拠出額 ×(所得税の限界税率+住民税10%)。
- 2027年想定の6.2万/月(年74.4万円)と、現行の2.3万/月(年27.6万円)の差額3.9万/月について:
- 合計**33%**レンジなら 約15.44万円/年 の“上乗せ節税”。
- 合計**30%**レンジなら 約14.04万円/年。
(※個々の税率帯でピタッと再計算するよ)
注意点(ここだけ確認)
- 60歳まで原則引き出せない=生活防衛資金は別に確保。三井住友銀行
- 退職金や企業型DCとの受け取りタイミング設計(一時金/年金)で控除の使い方が変わる。中央労働金庫
- 企業型DC加入者は併用時の上限の考え方が変わる見込み(合算で6.2万円)。制度詳細の最終確定は政令・省令にフォローアップ。厚生労働省
まとめ
- 老後“専用”を作り、節税の効きを最大化したいなら iDeCoが先。
- そのうえで、流動性・機動性は新NISAで補完、が実務的にいちばん強い。
あなた:
節税額に関してなんだけど月6.2万と月2.3万のそれぞれの節税額と、それにどのように戻る?控除される?のか教えて欲しい。
ChatGPT:
思考時間: 1m 26s
了解。結論からサクッといくね👇
まず式(超重要)
年間の節税額 ≒ 年間拠出額 ×(所得税の限界税率+住民税10%)
※iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」で課税所得からまるっと控除されます。
- 月6.2万=年74.4万
- 月2.3万=年27.6万
- 差額=年46.8万多く拠出
年間の節税額(代表的な税率レンジでざっくり)
(左:所得税/右:住民税10%。月額換算はおまけ)
① 合計30%(所得税20%+住民税10%)
- 6.2万:223,200円/年(約18,600円/月)
- 2.3万:82,800円/年(約6,900円/月)
- 差 分:140,400円/年(約11,700円/月)
② 合計33%(所得税23%+住民税10%)
- 6.2万:245,520円/年(約20,460円/月)
- 2.3万:91,080円/年(約7,590円/月)
- 差 分:154,440円/年(約12,870円/月)
③ 合計20%(所得税10%+住民税10%)
- 6.2万:148,800円/年
- 2.3万:55,200円/年
- 差 分:93,600円/年
「どうやって戻る/控除される?」(お金の動き)
① 所得税(その年に還付 or 調整)
- 秋ごろ、運営機関から**「掛金払込証明書」**が届く。
- 給与所得者:会社へ提出すれば年末調整で所得税が軽くなる/還付される。
- 年末調整に間に合わない or 個人事業:確定申告で控除→後日還付。
② 住民税(翌年6月から軽くなる)
- 住民税は“前年の所得”で決まるので、翌年6月以降の住民税天引きが毎月軽くなる(または普通徴収なら納付額が下がる)。
③ 社会保険料は別
- iDeCoは所得控除なので社会保険料には原則影響なし(=狙いは税の圧縮)。
補足(実務でよく躓くポイント)
- ふるさと納税の上限は、iDeCoで課税所得が下がるぶん小さくなる(=併用設計は要確認)。
- 受け取り時は退職所得控除 or 公的年金等控除の対象。将来の受け取り方(分割/一時金)と退職金のタイミングは事前に設計しておくとベター。
- 2027年に上限拡大(会社員“合算6.2万”、自営7.5万、加入70歳未満へ拡大予定)。老後専用ならiDeCo満額→余力を新NISAが基本線。
必要なら、小山の想定税率で
- 6.2万/2.3万/差額の年間・月間節税
- 10年・20年の累計節税見込み
まで一気に“ピタッ”と出すよ。
あなた:
33%なら 月6.2万=年74.4万投資すると 245,520円/年戻ってくる。
月2.3万=年27.6万投資すると 91,080円/年戻ってくる
ということでいい? バカでかい節税額よね
ChatGPT:
思考時間: 27s
その認識でOK!33%レンジ(所得税23%+住民税10%)なら――
- 月6.2万(年74.4万投資額) → 245,520円/年の節税
- 月2.3万(年27.6万投資額) → 91,080円/年の節税 ※ここ重要!!!!!!
「実質負担(手取りベース)」で見るとさらにインパクトが分かるよ:
- 6.2万コース:74.4万 − 24.552万 = 49.848万円/年(=実質約4.16万円/月)
- 2.3万コース:27.6万 − 9.108万 = 18.492万円/年(=実質約1.54万円/月)
どう戻る/どう控除される?
- 所得税:年末調整(会社員)or 確定申告でその年に還付/調整
- 住民税:翌年6月からの住民税が毎月軽くなる(前年所得で計算されるため)
注:この金額は「合計33%」での目安だよ。年の途中で税率帯が上下すると実額も連動して変わる。ふるさと納税の上限も“課税所得ダウン”で少し下がる点は頭の片隅に。
あなた:
節税されるは投資運用に関わらず確実に恩恵受けることになるメリットだが、60歳まで引き出せないデメリットだと思うんだけど、他に何かメリット、デメリットある?
ChatGPT:
思考時間: 4m 11s
いいポイントに目をつけてる。
「節税が“確実”」「60歳まで引き出せない」はド真ん中だけど、他にも押さえておきたいメリット/デメリットを要点でまとめるね。
iDeCoの主なメリット(節税以外も含む)
- 三重の税優遇:
①掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
②運用益は非課税(20.315%課税の対象外/特別法人税は現在“課税停止中”)
③受取時は退職所得控除(一時金)または公的年金等控除(年金)を使える。 iDeCo公式サイト+2iDeCo公式サイト+2 - 2027年前後の拡充が見込める:
会社員等の拠出上限は月6.2万円、自営業等は月7.5万円へ。**加入可能年齢は“70歳未満”**までに広がる方向(施行は公布後3年以内、運用開始時期は政令で決定)。 厚生労働省+1 - 資産の保全性:
金融機関が破綻しても、年金資産は信託分別管理で保護(投信は信託保全/定期はペイオフ枠)。 iDeCo公式サイト+1 - 差押えに強い“年金”性:
iDeCoの給付を受ける権利は差押禁止(ただし国税滞納処分は例外)。NISA等は対象になり得る点と対照的。 マネーブジュ.jp - iDeCo+(イデコプラス):
中小企業等が会社負担で上乗せできる制度(本人拠出+会社拠出で上限2.3万円、会社拠出は損金)。 THE OWNER - 手続きが少し楽に:
最近の見直しで**「事業主証明書」提出が廃止されるなど、加入のハードルが下がった。年末は払込証明書**で年末調整/確定申告すればOK(10月下旬以降に発行・電子交付も可)。 auのiDeCo(イデコ)+2楽天証券+2
iDeCoの主なデメリット/注意点
- 原則60歳まで引き出せない:
受給開始は原則60歳。ただし通算加入期間が10年以上必要で、短いと61~65歳へ繰下げ。60歳以降に初加入なら加入から5年経過後に請求可。 iDeCo公式サイト - 受取時の“10年ルール”に変化(2026年適用):
iDeCo一時金と退職金の控除重複調整期間が「5年→10年」に拡大。一時金と退職金を近接して受けると控除が調整されやすいので、受け取り順・時期の設計がより重要。 税理士法人AOIみらい|明るい未来を作る経営支援パートナー+1 - 必ずかかる手数料:
加入時2,829円、毎月171円(国民年金基金連合会105円+信託銀行66円)+運営管理手数料(多くのネット証券は0円)。受取・移換・限度超過の還付にも手数料あり。 マネックス証券+3iDeCo公式サイト+3楽天証券+3 - 運用面・事務面の制約:
①掛金額の変更は年1回まで ②運営管理機関の変更は2~3か月かかる ③他制度加入者は年単位拠出が不可になる等の細則あり。 iDeCo公式サイト auのiDeCo(イデコ) - 商品・コスト選びの難易度:
ラインナップや信託報酬は金融機関で差。コストの高い商品を選ぶと長期で効く。低コストのインデックス中心が定石。 投資信託協会 - 設計上の副作用:
課税所得が下がるためふるさと納税の上限等は小さくなる(=併用時は上限計算の見直しが必要)。
まとめ(実務感)
- 老後“専用”の器としてiDeCo優先はやっぱり強い。
- ただし流動性ゼロの代わりに設計力が問われる(受取の“10年ルール”、退職金のタイミング、商品コスト、手数料、掛金変更の頻度など)。
- 2027年の上限アップ(6.2万/7.5万)・70歳未満加入を見据え、まずは現行枠を回しつつ受取設計まで一緒に詰めるのがベスト。 厚生労働省+1
必要なら、小山の退職金予定時期も聞かせて。iDeCoの一時金/年金の最適受け取り(“10年ルール”回避案を含む)と、新NISAとの資金配分まで一気にシミュレーションして数値を埋めるよ。
あなた:
大体書いたかね?重要な部分
ChatGPT:
思考時間: 1m 31s
うん、重要どころはほぼ押さえたよ。仕上げ前の“最終チェックリスト”置いとくね👇
最重要ポイント(OK / 追記推奨)
✅ 老後目的だったら「iDeCo優先→残りを新NISA」
- iDeCo:掛金は全額所得控除、運用益非課税、受取時も控除(退職所得控除 or 公的年金等控除)。iDeCo公式サイト
- 新NISA:無期限・年間360万円/生涯1,800万円、売却で総枠(簿価)再利用可(同年内の年間枠は復活しない)。金融庁
✅ 2027年前後のiDeCo拡充(必須レベル)
- 会社員など:月6.2万円へ(合算上限)/自営:月7.5万円/加入年齢は70歳未満へ拡大予定(改正法成立、施行は公布後3年以内の政令)。厚生労働省+1
✅ 節税額の“ピタッ”計算例(33%想定)
- 月6.2万(年74.4万)→ 24.552万円/年
- 月2.3万(年27.6万)→ 91,080万円/年
※還付・減税の入り方:所得税はその年の年末調整/確定申告、住民税は翌年6月から軽くなる(説明済みでOK)。iDeCo公式サイト
✅ デメリットの芯
- 60歳まで原則引き出せない(老後“専用口座”に向く)。iDeCo公式サイト
ここも入れると完璧(重要アップデート)
- 受け取り時の“10年ルール”
iDeCo一時金→退職金(両方一時金)の順だと、2026年1月以降は「10年以上」間隔を空けないと退職所得控除が満額使えないケースが出る。出口設計の注意喚起を一言。野村アセットマネジメント+1 - 企業年金との併用の考え方
新制度は**「合算で6.2万円」**が軸になる見込み、と整理(最終詳細は政令・省令フォローの文言も一言)。楽天証券 - “制度としての安全性”の一言
iDeCo資産は年金資産としての扱い・受取時に控除がある旨はすでに触れてるが、公式のiDeCoサイトへの参考リンクも末尾に添えると読者安心。iDeCo公式サイト - NISAの枠の誤解つぶし
「無期限+枠再利用=万能ではない。年間360万円の当年枠は復活しない」を注記。金融庁
仕上げの“見出し”提案(本文に差し替え可)
- 結論:老後はiDeCo優先、流動性は新NISA
- 2027年のiDeCo拡充(6.2万/7.5万・70歳未満)
- 33%想定で見る:月6.2万/2.3万の節税額
- お金の戻り方(年末調整・確定申告/翌年住民税)
- デメリットと対策(60歳縛り/10年ルール/商品コスト)
- 実装:今年〜2026年の配分、2027年以降の満額プラン
- まとめ&参考リンク(金融庁NISA特設/厚労省改正法/iDeCo公式)
このチェックでOKなら、会話台本→図表(早見表)→X用告知文まで一気に書き上げるよ。必要なら“33%想定”の10年・20年の累計節税も入れて可視化する。 金融庁+2楽天証券+2
僕の認識ですが、老後資金を目的とするなら、新NISAよりも確実に恩恵(月掛け金6.2万 年74.4万なら→ 節税額、確実に戻ってくる24.552万円/年)があるからiDeCoをやるべきだが、60歳まで引き出せないというデメリットはデカすぎるデメリットであると思うからみんな嫌煙するのだと思う。でも、74万投資して、確実に24万戻ってくるのは高くないですか?とは思う。
何かちょっと見づらいかもしれませんが、
- 月6.2万(年74.4万投資額) → 245,520円/年の節税
- 月2.3万(年27.6万投資額) → 91,080円/年の節税
ここ!
ここだけでもすごくないですか?
744000円投資すると、確実に245520円帰ってくる。普通に投資してたらこんなことはありません。こんなに確実に恩恵があること何てありません。
しかも744000円投資も出来ている。
こんないい制度はないんです。
📈 節税しながら将来に備えるなら、iDeCoやひふみ投信などの積立投資が王道です。